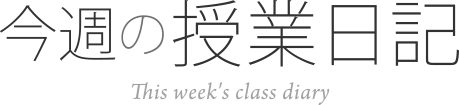社会科教育法
[対象学年] 児童教育専攻2年(教職必修)

社会科教育法では、小学校社会科授業の在り方について研究し、教材研究や学習指導案作成、模擬授業等を通して問題解決学習の授業づくりを実践的に学んでいきます。
本時では、小学校の歴史授業の模擬授業を実際に体験することで問題解決学習の大切さを実感してもらうことをねらいとしました。
主な学習展開は、縄文時代の日本で人々はどこにたくさん住んでいたかを予想し、資料をもとに縄文時代の季節と食料、獲得する手段や道具、調理方法などを班などで検討していきました。
その後、小学校の歴史学習のなかで熊本県の歴史を学んでいけるような内容の資料を検討していきました。
学生の皆さんは、全学年のすべての単元を班毎に担当して模擬授業の構想を練っています。これからどんな授業を展開してくれるか、とても楽しみです。


学生の感想
・今回の先生の授業を通して、社会科の学習は「知識を教える」教科ではなく、「考える力を育てる」教科であると改めて感じた。そのためには、教師自身が十分な知識をもとに教材を吟味し、児童の興味を引き出す工夫をしながら授業を構成することが必要だと思う。私も模擬授業の準備を進める中で、児童が「なぜだろう」と思える問いを大切にし、自分の力で発見する楽しさを感じられる授業を目指したい。
学生の感想
この模擬授業を体験して、歴史の授業は単なる過去の出来事を覚える教科ではなく、過去のことと今とをつなげて考える教科であると感じた。将来、教師として歴史を教えるときには、児童が自分で考え、地域に誇りをもてるような授業を目指したいと思う。そのためには、地域教材の収集や問いづくりの工夫を重ね、児童の興味を引き出す授業づくりを心がけていきたい。
学生の感想
私は、「わかった」という実感と「考える力」を育む授業を目指したいです。そのためにはまず、子どもたちの興味を刺激する「問い」を授業の中心に据えることが重要だと考えます。そして、その問いを解決するために、ただ聞くだけでなく、自分の意見をしっかり出し合い、協力して考える活動を増やすべきだと先生の授業からも感じました。さまざまな資料から、子どもたちが多角的な視点から社会や歴史を捉えられるような環境を作りたいと思います。今回の講義を通じて感じたこと考えられたことを忘れず、子どもたち一人ひとりが主体的となり、自ら学びに向かう力を育てることができるよう、頑張りたいと思います。
学生の感想
今回の講義資料を通して、地域の史料や遺跡を教材として活用することで、教科書だけでは伝わりにくい歴史の具体的な姿を児童に示すことができる点が印象的であった。熊本平野の縄文海進や貝塚、古墳の石材の産地など、地域に存在する史料を取り入れることで、児童は生活や環境とのつながりの中で歴史を理解でき、単なる暗記ではなく、自ら考える学びが生まれることを実感した。